![]() パソコンの仕組み
パソコンの仕組み
パソコン本体は、ほかの家電に比べるとやや大きく、ケーブルもたくさんあり、
中に何が入っていてどういう仕組みになっているのか、知りたくなったことがあると思います。
そんな人のためや、パソコンのことをわかりたいので、是非内部のことも学びたい!という
人向けに、このページを作りました。全部頭に入れた上で、PC講座のコーナーを読むと、結構
理解できると思います。最初はわからなくても、何回か読んでいくうちにわかってくると思います。
まず、パソコンはたくさんの部品やICチップなどでできています。
それらの部品がケーブルで結ばれ、そのケーブル内を電気信号が通っているわけです。
下に、具体的なパソコンの中の部品と配線を書いてみました。
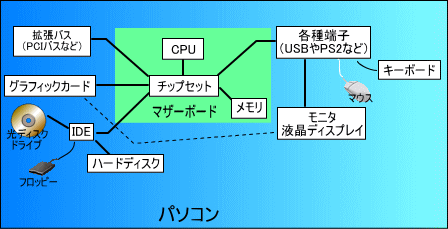
CPU:中央処理演算装置、という物で、人間でいうと脳の役割をします。
ほとんどの処理や計算は、このCPUというチップが行います。
よく、CMで流れている「Pentium4」も、このCPUのことです。
最近のパソコンには、Pentium3やCeleron、DulonやAthlonという名前のCPUがよく搭載されています。
大きさは結構小さくて、5cm×5cmくらいの物が主流です。下にピンが並んでいて、それが
CPUソケットというソケットに刺さっています。CPUソケットはマザーボードにあります。
マザーボード:パソコンの部品をのせるための、大きな板と考えるといいでしょう。
このマザーボードにCPUソケットやチップセット、BIOSといった部品がのっています。
メモリも、メモリソケットがマザーボード上にあります。
チップセット:この部品が、いろいろな電気信号を所定の場所に分けてくれます。
言い換えれば、交差点の交通整理の人、みたいな感じです。
安いPCのチップセットの中には、グラフィック機能が内蔵されたタイプもあります。
メモリ:CPUが作業をするために使う一時利用としての場や、OSやソフトが
作業するための一時利用場所として利用される物です。PCの電源が入っている間だけ、
内容を保存する事ができます。PCを使う上で表面的には見えませんが、大切な部品です。
グラフィックカード:グラフィックカードに搭載される2D/3D用のチップがパソコン内の電気信号を
処理して、モニタに写る様に信号を処理します。
この絵の場合は、AGPバスというグラフィック専用バスの上にカードがある、と考えます。
これがPCIバスの場合もあります。
モニタ・液晶ディスプレイ:グラフィックカードから送られてきた信号を、人間の目に見えるように変換し、
写しだすものです。グラフィックカードから出ている端子にプラグをつなぐタイプと、
パソコンから出ている端子にプラグをつなぐタイプの2種類があります。
また、液晶ディスプレイにはアナログとデジタルの2種類のタイプがあります。
IDE:パソコンの内部の部品をつなぐためのチップと考えます。
これにハードディスクやCD-ROMドライブなどがつながっています。
光ディスクドライブ:これがCD-ROMドライブやCD-RWドライブ、DVD-ROMドライブやMOなどにあたります。
フロッピーディスクドライブ:その名の通り、有名なフロッピーという外部記憶ディスクが扱えるものです。
拡張バス:デスクトップ型(大きいPC)はPCIバス、ノート型PCではPCカードがこれにあたります。
ここにいろいろなカードを刺して、パソコンの機能を拡張する事ができます。
各種端子:いろいろな外部の周辺機器をつなぐ為の端子のことです。
USBや、パラレル(プリンタを繋ぐ)、シリアル(TAやモデムをつなぐ)、PS2(マウスやキーボード)
などの名前の端子のことです。
これらが、パソコンの中には存在します。直感でわかるのは、CD-ROMドライブやマウス、キーボード、
モニタ・液晶ディスプレイくらいだと思います。後は、パソコンの中で処理をしているチップ類なので、普段は見えません。
わからないPC用語は、左の部分にある用語集で調べてみてください。
今わからなくても、パソコンを使っている間に、わかるようになってくると思います。
![]()
![]()
![]()
このページはTOPページではありません。このページへの直リンクは禁止します。
(C)2000-2001,Tako2